サイン波 (Sine wave)
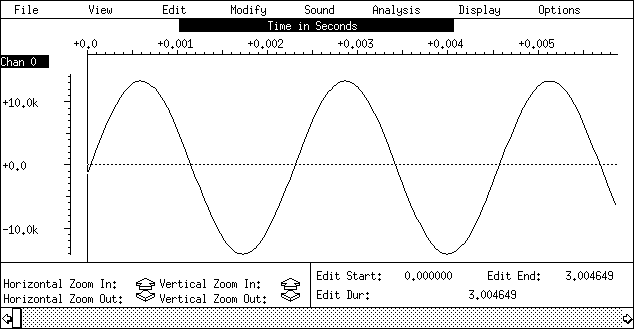
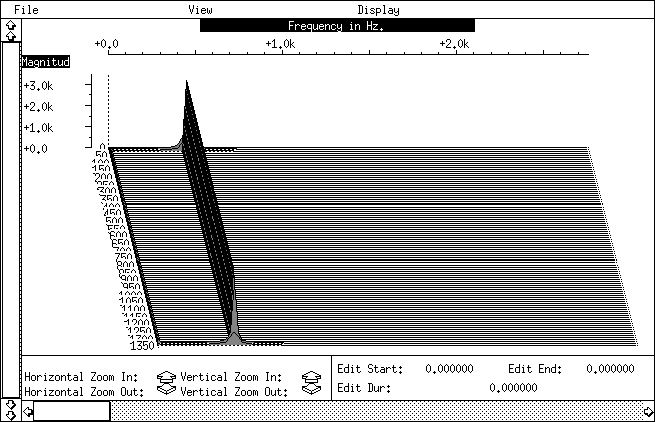
矩形波 (Square wave)
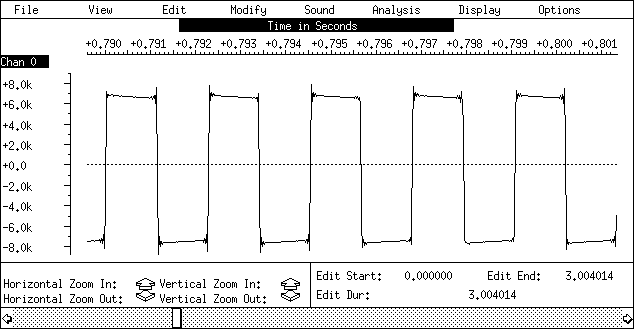
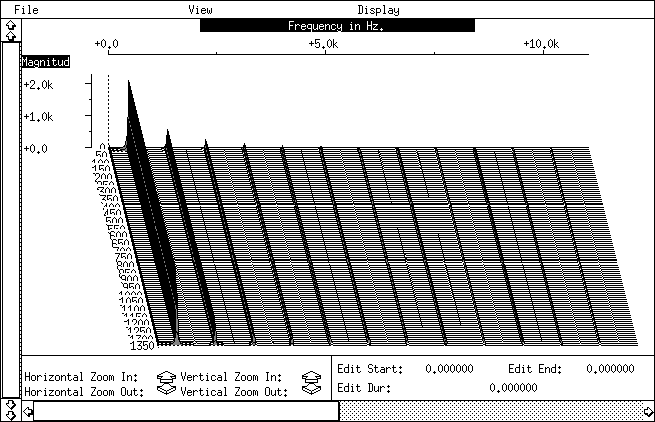
論より実際。音を出して見ましょう。 (以下の[MP3]のボタンでは「MP3オーディオファイル」の音が聞けます)
まず 周波数発振器(TRIO製の「AG-202A」)で
サイン波と矩形波を調べて見ましょう。
周波数は442[Hz](約3秒間・サンプリング周波数44,100[Hz]・16Bits)です。
左から MP3再生ボタン・音の波形図・そしてそのFFT(フーリエ変換)
グラフです。
(FFTには「MiXViews(mxv)」というソフトを使用しました。
左右が周波数の高さ上下が音の大きさ そして前後が経過時間を表しています。
図はクリックで拡大されます)
シミュレーションと違い FFTは棒グラフとはならず
多少丸みを帯びています。
しかし サイン波では倍音はなく 同じ音が同じレベルで続いてるのが
分かると思います。
また 矩形波は奇数倍のサイン波の集まりとのことで
1・3・5〜(442・1326・2210〜)の倍音があることが分かります。
ピアノの音です。 (マイクロフォンと音響空間の影響を避けるため 電子ピアノ(pf-15)「PIANO-2」の音源を 直接パソコンに接続して使用しています。 サンプリング周波数44,100[Hz]・16Bitsです。)
C40
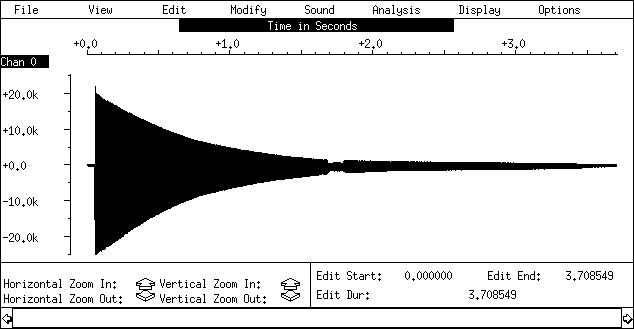
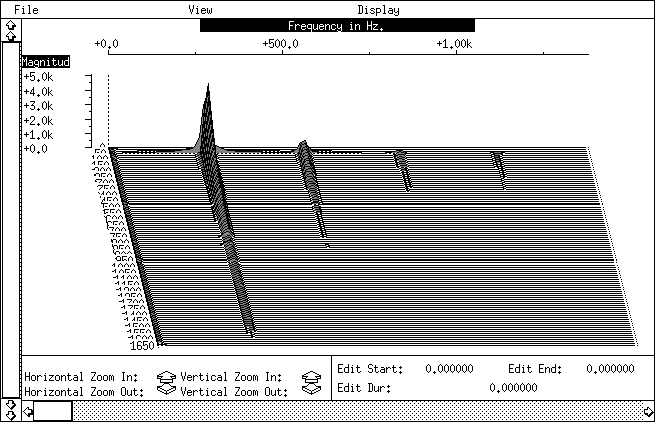
C40 - G47
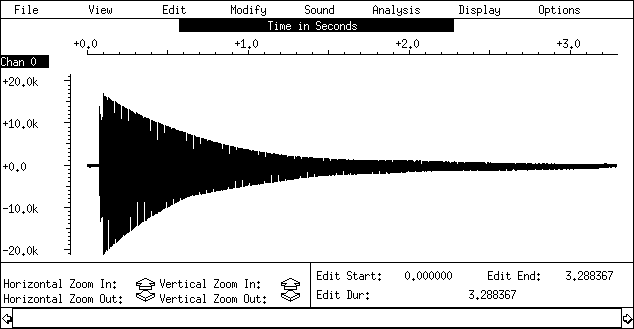
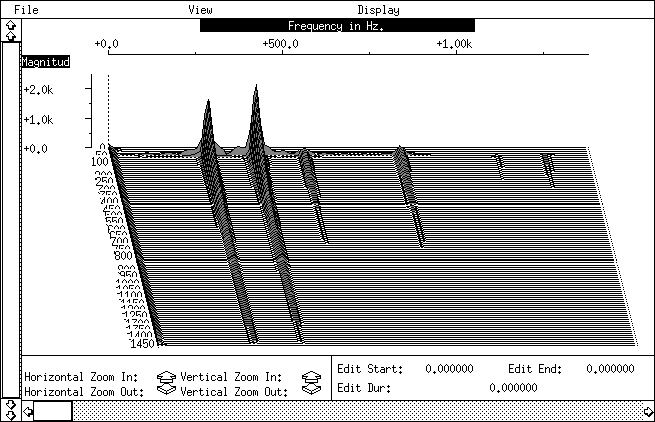
5度 C40(約262[Hz])と G47(約392[Hz])の3対2の倍音 786[Hz]付近に音量の増加など見れるでしょうか?
C40 - E44 - G47 3和音です。
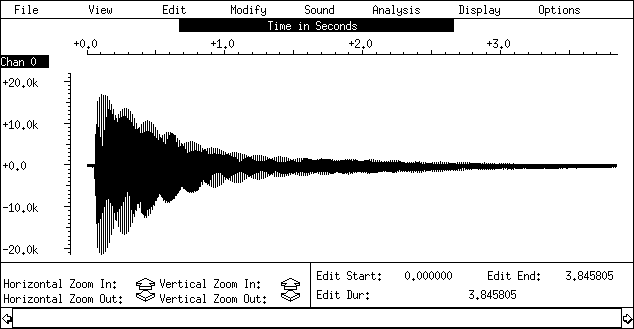
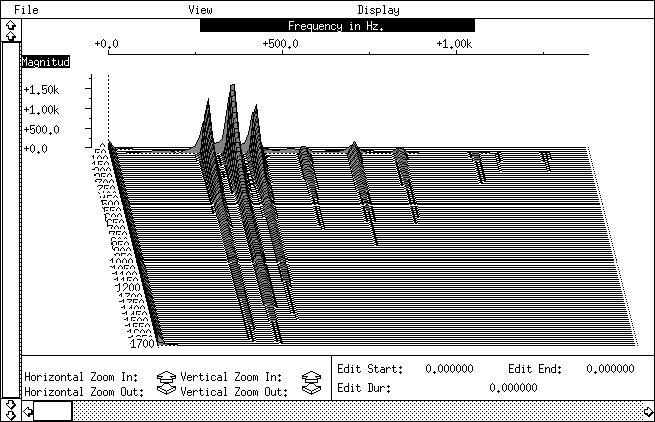
少し複雑な和音です。
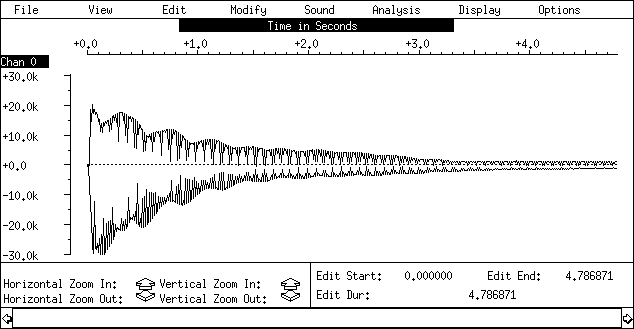
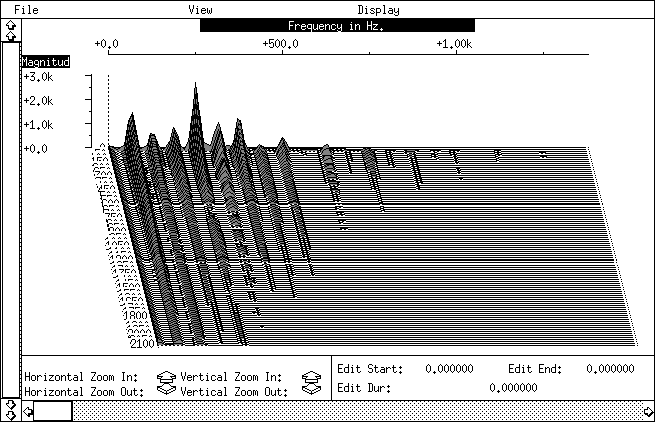
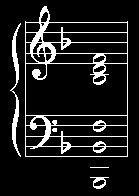
CDからの ピアノの音を聞いて見ましょう。
(使用されている楽器は明記されてはいません。
録音は1989年です)
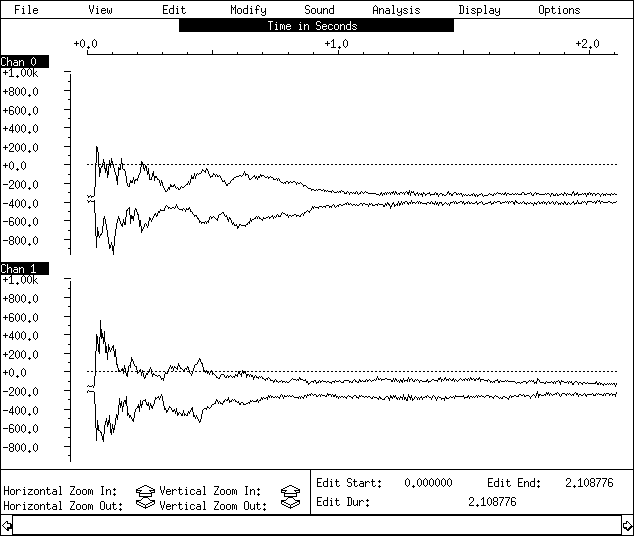
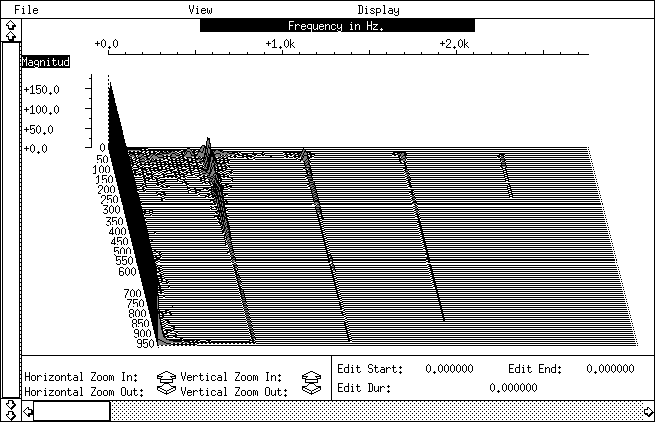
C#(53)の単音で およそ554Hzぐらいのはずです。
FFTグラフでは 基音から4倍音まである事が分かります。
その音の始まり部分を拡大して見ます。
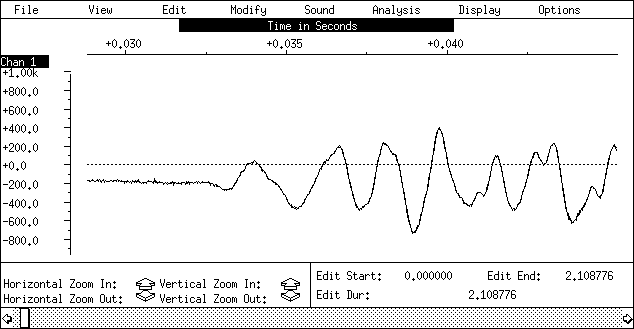
以下 順次部分音を拡大して見ます。
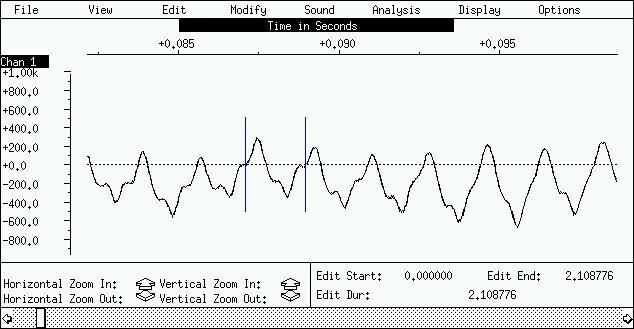
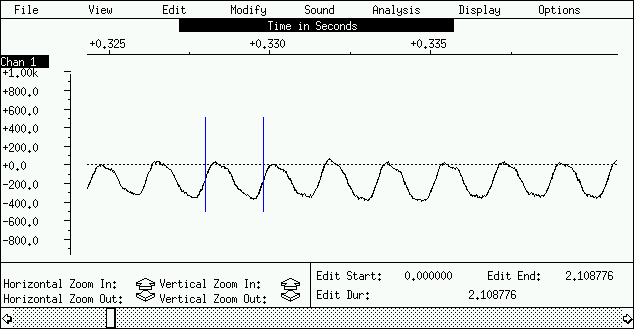
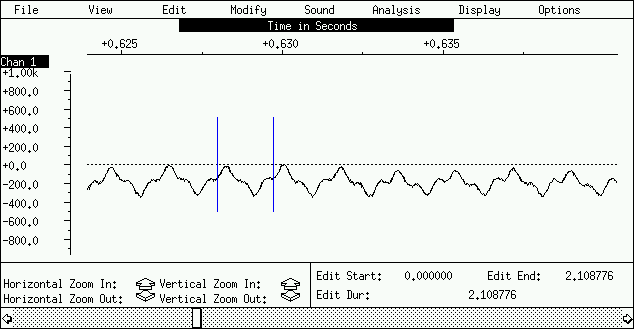
グラフに青い縦線で示しているのは 1サイクルの始めと終りの位置です。
ピークからピークを見ると 鋸波形とも思われますが
音の立上りの中央から見ると 立上りが急で下りが緩やかな
波形もある事が見えます。
そうした波形を「振動と波動」の “音の合成”で試して見て下さい。